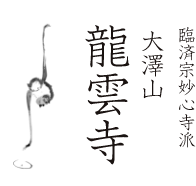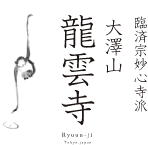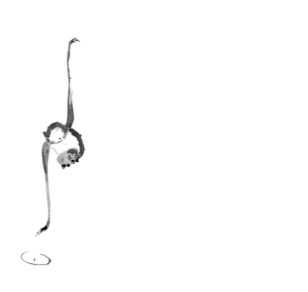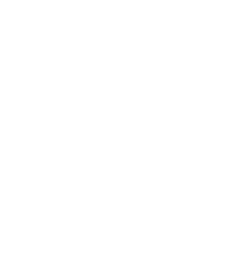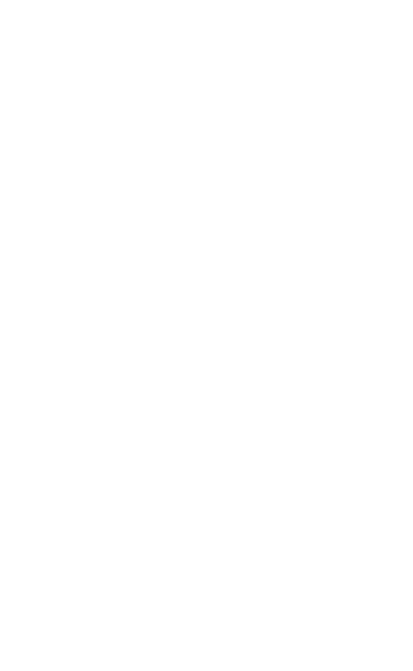この語には面白い因縁話があります。唐の文宗皇帝が、人は炎熱に苦しむ我は夏日の長き事を愛すと、起承の句を作ったのを受けて詩人である柳公権が、転結の句を作って一篇の詩といたします。
薫風自南来 殿閣微涼を生ず
世間一般の大多数の人々は夏の日のカンカン照りの暑さを厭がるけれども、私はその夏の日が一年中で一番長いのが大好きである。暑い暑いといっても、時折り木立を渡ってそよそよと吹いてくる薫風によって、さしも広い宮中もいっぺんに涼しくなり、その心地よさ、清々しさはむしろ夏でないと味わえないというわけです。
しかし、約200年後、宋の詩人、蘇東坡は、この詩には残念ながら為政者として庶民への思いやりがない。すなわち、風も通さぬウサギ小屋のような小さな家に起居し、炎天下、農耕に、商売に精を出さねばならない一般庶民の苦しさを忘れて、夏の長い日を広々とした宮中で遊んで暮らせばよい皇帝の思い上がりの詩であると批判し、当時の上流階級の人々への風刺を込めて一篇の詩を作ります。
一たび居の為に移されて 苦楽永く相忘る願わくは言わん此の施しを均しくして
清陰を四方に分かたんことを
皇帝陛下は生まれながらにして広々とした宮中に住んでおられるので、天下の人々が炎熱の中に苦しんでいるのに気が付かないのです。どうか、もっと天下万民の上に思いを寄せ『薫風自南来殿閣微涼を生ず』のような楽しみ、安らぎを人々に分かち与えてこそ、皇帝ではないでしょうか。大慧禅師はこの語を聞いて大悟したといわれます。私たちは何かというと損失にこだわり、利害にとらわれ、愛憎にかたより善悪にこだわり、迷悟にとらわれ、凡聖にかたよって、右往左往する毎日です。しかし、それらの対立的観念を一陣の薫風によって吹き払ってしまえば、こだわりもなく、とらわれもなく、かたよりもない、自由自在なサッパリとした清々しい涼味を感じることができます。そのカラッとした、一切の垢の抜け切った無心の境涯を”殿閣微涼を生ず”と詠ったのです。
禅語集
1
薫風自南来、殿閣微涼を生ず
薫風自南来 殿閣生微涼
【枯木再び花を生ず -禅語に学ぶ生き方-】
細川景一 著より