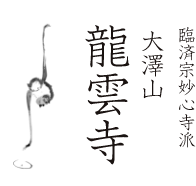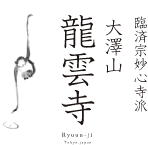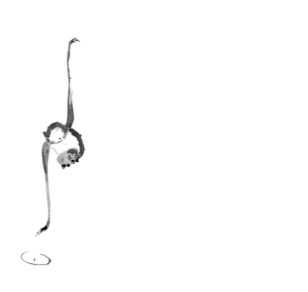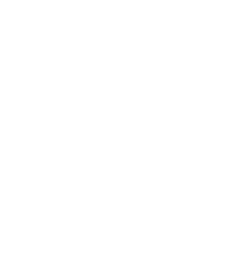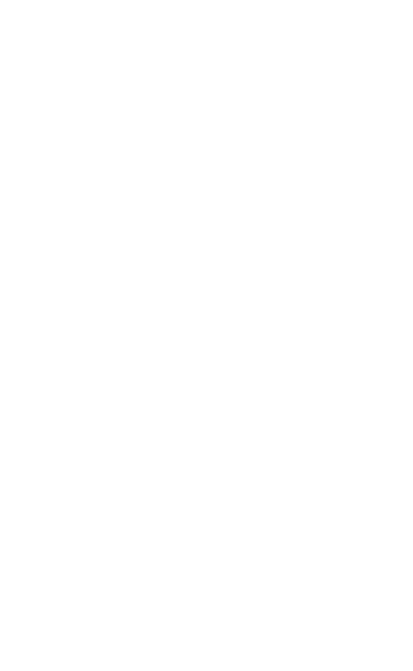有時奪人不奪境、有時奪境不奪人、有時人境倶奪、有時人境倶不奪
僧有り問う、「如何なるか是れ奪人不奪境。」師云く、「煦日発生して地に鋪く錦、○孩髪を垂れて白きこと糸の如し。」僧云く、「如何なるか是れ奪境不奪人。」師云く、「王令已に行われて天下に○し、将軍塞外に烟塵を絶す。」僧云く、「如何なるか是れ人境両倶奪。」師云く、「并汾絶信、独処一方。」僧云く、「如何なるか是れ人境倶不奪。」師云く、「王、宝殿に登れば、野老謳歌す。」
臨済禅師はある日、説法で衆に向かって示された。「有る時は奪人不奪境、有る時は奪境不奪人、有る時は人境倶奪、有る時は人境倶不奪」これが「臨済四料簡(揀)」といわれるもので「料」ははかるの意、「簡」も「揀」も分別、選択するの意、「四料簡」とは私達の日常生活の中での、四つの悟りの型といったところです。
「人を奪って境を奪わず」まず人とは見る主体、自分のこと、境とは見られる客体、すなわち、目前に羅列する森羅万象一切のことを意味します。しかし、この「人」と「境」は対立しているようですが、本来的には「一無位の真人」が入っては主観の「人」になり、出ては客観の「境」となる関係です。奪とは立たせざること、すなわち否定し去ってしまうこと、「不奪」とはその反対に立すること、肯定することです。「人を奪って、境を奪わず」は、自己を空しくして万境に没入し去って、一体一枚になることです。大自然と一体の境涯をいいます。 日本南画界の長老、直原玉青画伯は語っています。
「絵を描くものは一枚の画紙の中に小さな理想郷、小さな宇宙を創造することです。花に対して自ら花に、山に対して自らが山になり、自然の心に同化し初めて自然の心が解るのである。花の真実、山の真実を知るために、写生が大切である――。幾度か繰り返し、繰り返し自然に同化し、「我」が滅却できれば、自ずと気韻が生動し、用筆の妙趣が生れます」これこそが奪人不奪境の妙境です。
「」とは春の陽日、「」とは生れたばかりの赤ちゃんのこと、寒い冬も終わり春ともなればポカポカ陽気、桜を始め百花が一斉に咲いてまさに、「見渡せば柳桜をこきまぜて都ぞ春の錦なりけり」の風情です。「?孩髪を垂れて白きこと糸の如し」真っ白い長い髪の赤ちゃんなど存在しません。人の存在を否定して春景色一色をいおうとしているのです。自分を忘れて春爛漫の景色に見とれている消息です。
第二は「奪境不奪人」境を奪って人を奪わずのところは、目前の万境を否定し去って、自己の胸中に呼吸して絶対的な自己一人のみの世界です。天上天下唯我独尊、乾坤只一人、といった大きな自分を感得することです。しかし、それはお山の大将俺一人といった、思い上がりではありません。それは目前に羅列する一切の存在の中に自分を見い出すことです。一草一木に自分の命を発見することです。
東山魁夷画伯はある随筆の中で、「足もとの冬の草、私の背後にある葉の落ちた樹木、私の前には果てしなくひろがる山と谷との重なり、この私を包む天地のすべての存在は、この瞬間私と同じ運命にある」と書いてます。
目前の森羅万象の一つひとつが自分以外の何物でもない事を感得されています。「王令已に行われて天下に?し、将軍塞外に烟塵を絶す。」「塞外」とは国境のこと、「烟塵」とは狼烟馬塵のことで、狼烟とはのろし、馬塵とは馬が走り回ることで烟塵とは戦いの意、王の命令が国の隅々まで行き届いて、天下は泰平そのものである。国境を守る守備隊の将軍たちも異民族を抑え込んで戦いも無く静かなものであるというわけです。すなわち天下国家、万民総出で掌握し尽くして乾坤只一人の消息、これこそが「奪境不奪人」のところだというわけです。「奪人不奪境、奪境不奪人」の二つは味方の相違はあるけれど、自己と万法が一体一枚、一如の消息をいうわけです。
第三は「人境両倶奪」人境両つ倶に奪うの消息です。この「人境両倶奪」は今迄の二つとはすこし違います。修行者は最初の公案の「趙州狗子」の則に参じて、ただひたすらに坐禅に努めます。
時に純熟して突然、目前の森羅万象が崩れ落ち、自己も天地もないところ、すなわち、立って立つべき自己も無く、また、立つべき大地もない、自己と万物がことごとく、消殞し尽くした消息を得ることができます。この一切を無にしたところを「人境両不倶奪」というのです。その境涯は「壁立万仭」(四方八方が切り立った険しい崖)、釈迦といえども達磨といえども、誰も近づくことも寄り付くこともできない厳しい消息です。
鎌倉円覚寺の開山、無学祖元禅師(一二二六~一二八六年)は南宋末期の禅僧です。中国、温州能仁寺に在住の折、元兵の侵攻に遇います。一山の僧たちは逃げ出しますが、無学祖元禅師は方丈にどかっと坐して泰然自若、禅定三昧に入ります。群がり囲んだ元兵の一人が大刃を揮って、師の首を切ろうとします。
乾坤、地として狐?を卓するもなし
喜び得たり、人空、法も亦空
珍重す大元三尺の剣
電光影裏に春風を斬る
―この広大無辺の大地もただ一本の杖を立てる余地もないほど、「元」の天下になった。どこかへ行けといわれてもどこに行くこともできない。しかし、私は一切皆空の理を体得出来たので、執着するものとて何一つない。名刀で私を斬るのは、あたかも稲妻がピカリと閃く間に春風を斬るようなもので、何と手応えのないことだろうよ。死ぬもよし、生きるもよし―と、無学祖元禅師は一喝を浴びせます。その威厳に圧された兵は逃げ出します。人も境も奪い去った、恐ろしいまでも厳しいところです。
「絶信、独処一方。」と答えます。并汾とは山西省にあった「并洲」と「汾洲」の国の名、唐の時代に呉元済という人が反乱を起こし、并洲、汾洲の城を占領し、城主を殺したことがあります。そのとき城の様子(境)、人びとの安否(人)の一切の消息を絶ってしまいました。それでも人も境も倶に奪ったところを「并汾絶信、独処一方。」というのです。
第四は「人境倶不奪」人境倶に奪わず、です。人も境も奪わず、見る自分も存在し、また見られる万法も存在し、しかし互いに犯さない、人も境もそのままの姿で共栄共存、徹底的な肯定の世界です。あれもよし、これもよし、あるがままに生きていく、しかも規を越えず、きちんと法を守っていく世界です。
日々 日々 また日々
閒に 児童を伴って この身を送る
袖裏に 毬子 両三箇
無能 飽酔 太平の春
―毎日毎日、子供達と遊んで日を送る。たもとには、いつも三個の球が入っている。バカな自分は今日もまた、酒に酔って太平の春を楽しんでいる―良寛和尚の詩です。気ままに子供と遊んで暮らす凡夫と同じ様な毎日の生活の中に、驚くほど高く澄んだ境地が見えます。人境、共に奪わざるの端的です。
「王、宝殿に登れば、野老謳歌す。」国王が庶民の生活を思い高楼に登ってどんなものか心配そうに眺めると、農夫たちが田畑で農耕に励みつつ、国王の徳と平和な世の中を讃えて謳歌しているところです。臨済禅師は国王と農夫がそれぞれ分を守って、互いに犯すことなく生活を楽しむ様子、すなわち、天下泰平、君臣和楽(君主と国民がお互いに和して楽しむ、平和そのものの様子)の消息を「人境倶不奪」というわけです。 中国に「十八史略」という書物がありますが、その中に「鼓腹撃壌」という話があります。尭帝の時代、尭帝は即位以来五十年、ひたすら善政を施しますが、民の様子が気がかりで、自分の目と耳で確かめようと町にでます。とある街角で子供たちが唄を歌っています。
我が烝民立つる
爾の極にあらざるはなし
識らず知らす
帝の則に順う
―天子さま、私達がこうして元気に暮らすのはみんなあなたのお蔭です。天子さま、私達はこうやって、何も知らずに気にもせず、みんなあなたを頼ります―
帝はそれを聞いて、どうもしっくりいきません。しばらく進むと、一人の老人が撃壌(壌、木ごまをぶつけあって勝負を決める遊び)を楽しみながら、腹を叩いて拍子を取って楽しげに歌っています。
日出でて作き
日入りて息う
井をほりて飲み
田を耕し食う
帝力我に何かあらんや
―日が出りゃ、せっせと野良仕事、日暮れにねぐらで横になる。のどの渇きは井戸を掘ってしのぎ、腹の足しには田畑のみのり、天子さまなぞおいらの暮らしにゃ、あってもなくてもおんなじよ―
天子さまを有り難がっているうちは本物ではありません。天子さまなど関係ないといい切るところに、本当の政事が行われているのです。これが人境倶不奪の天下泰平の消息というのです。
以上が四料簡といわれるものです。私達の生活のなかで、自分とそれに対する境とのかかわり方、これを自在に応用するところに禅心のある生活があるのです。